なぜ幸せになりたいという願いが幸福を遠ざけてしまうのか?
「幸せになりたい」という思いは人間であればごく自然な感情だろう。しかし幸せになりたいと強く願うほど幸福は遠ざかる。その思いが強ければ強いほど、幸福は砂のように指の間からこぼれ落ちていく。
なぜなら、その「幸せになりたいという執着」が人生を不幸に染めるものの正体だから。
これは単なる精神論や道徳の話ではない。心理学的な知見においても、こうした心の状態が現実や行動に大きな影響を与えることが明らかになっている。
今回は幸せを強く求めるほど幸福が遠ざかる理由について、心理学の観点を交えながら解き明かしていくので、ぜひ最後まで読み進めてほしい。
幸せになりたいという心理の裏側にあるもの
幸せになりたいという思いの裏側には、どのような心理が隠れているか考えたことはあるだろうか 。幸せを強く願う人の深層心理にある思い ──それは「今の自分は満たされていない」という欠乏感だ。
これは足りないものや満たされていない部分ばかりに意識が向き、いまの自分に与えられている恩恵に気付けていない心理状態といえる。
現代に生きる我々は人類史上稀に見るほど恵まれた環境を生きている。しかし多くの人はその環境を「当たり前」と認識している。たとえば以下のような事柄がそうだろう。
- 雨風をしのげて安全を確保できる住まいがある
- 美味しいご飯をお腹いっぱい食べられる
- 蛇口をひねるだけで浄水処理された水が出る
- エアコンのボタンひとつで部屋を快適な温度に保てる
- 戦争のない平和な国で自由に生き方を選べる
- 世界中の情報に簡単にアクセスできる
こうした恩恵は本来、決して当たり前ではない。世界には今なおこうした環境が手に入らない国や地域が数多く存在する。
それに気付けず、「もっとお金が欲しい」「称賛されたい」「恋人が欲しい」と、さらなる刺激や欲望の充足を追い求める。これが幸せを強く求める人の深層心理に潜む思いといえるだろう。
ドストエフスキーの『悪霊』にある一節は、まさに人間の強欲さと愚かさを示している。
人間というものは不幸のほうだけを並べたて、幸福のほうは数えようとしないものだ。
『悪霊(2)』(p.82)|光文社|フョードル・ドストエフスキー
幸せになりたいと強く願うほど幸福が遠ざかる心理学的なメカニズム
多くの人が人生は思い通りにならないと考えているが、じつは逆だ。人生は自分が心の奥底で信じている通りにしかならない。
米国の作家・アール・ナイチンゲールはこう語る。
今のあなたの環境は、これまでの人生であなたが考えてきたことのすべてを表している。
『人間は自分が考えているような人間になる(p.41)』|きこ書房|アール・ナイチンゲール
自分が心の奥底で信じていることは、その信念に沿った行動や態度を引き出す契機となり、結果的に深層心理にある思いが現実になりやすくなる。これを心理学では「予言の自己成就(self-fulfilling prophecy)」と呼ぶ。
予言の自己成就(self-fulfilling prophecy)
予言の自己成就とは、根拠のない考えや思い込みであっても、それを信じることで生じた行動が結果的にその予測を現実化してしまう現象だ。
たとえば「自分は人前でうまく話せない」と思い込んでいると、その不安によって緊張が生まれ、結果的に本当にうまく話せない状況になる。反対に「自分は人前で堂々と話せる」と信じていれば、自然と自信のある態度や行動が生まれ、結果として話がスムーズに進む。
自らの信念が行動を生み出し、その行動が結果をつくる要因となり、その結果がまた信念を強化する。こうして自分の心の奥底で信じていることが現実になっていく。
つまり「幸せになりたい」という思いの強さは欠乏感の裏返しであり、その「満たされていない」という深層心理が無意識のうちに選択や行動を決定する。そして予言の自己成就によって本当に満たされない現実を自らつくり出してしまうのだ。
では、その信念はどのように形成されるのだろうか。その要因といえる現象のひとつが「カラーバス効果(Color Bath Effect)」だ。
カラーバス効果(Color Bath Effect)
カラーバス効果とは、「意識を向けていることが目に入りやすくなる」という人間の心理的傾向だ。たとえば「赤い車が欲しい」と思った瞬間、街中で赤い車ばかりが目につくようになる現象がその一例といえる。
「幸せになりたい」という思いの裏にある欠乏感も同じだ。
「もっと欲しい」「もっとこうだったら」など、欠乏感に意識が向いていると日常の中で「幸せでない証拠」ばかりが目に入りやすくなる。その結果、ますます欠乏感を強化してしまうのだ。
この欠乏や不足に意識が向いてしまう要因として、「理想と現実の不一致」が挙げられる。
この理想自己と現実自己のギャップが心理的な不安やストレスを引き起こすという考え方を「セルフ・ディスクレパンシー理論(Self-Discrepancy Theory)」と呼ぶ。
セルフ・ディスクレパンシー理論(Self-Discrepancy Theory)
セルフ・ディスクレパンシー理論は1987年に心理学者エドワード・トーリーによって提唱された理論だ。この理論では人が持つ「自己概念」を3つに分類している。
- 現実自己(Actual Self)
自分が現在持っている特性や状態。 - 理想自己(Ideal Self)
「こうありたい」と願う理想像。 - 義務自己(Ought Self)
「こうあるべき」と感じる道徳的・社会的義務に基づく自己像。
たとえば「経済的に自由な生活を送りたい」という理想と「現実は支払いに追われている」という状況とのギャップは慢性的なストレスを生み出す。つまり理想と現実の差が大きければ大きいほど不足や欠乏を意識しやすくなり、日常の中でその「不幸の証拠」ばかりを拾ってしまう。
こうしてカラーバス効果で欠乏感が強化され、予言の自己成就で「満たされていない」という信念に基づく無意識の選択と行動が生じ、幸福を遠ざけてしまう負のループが完成するのだ。
これが幸せになりたいと強く願うほど幸福が遠ざかる心理学的な理由だ。
幸福な人生に必要なのは「足るを知る心」
幸福な人生を歩むためには、「これ以上必要なものなどない」という逆説的な気づきが必要となる。
知足者富(足るを知る者は富む)
『老子(p.102)』|講談社|池田知久
これは中国の古典『老子道徳経』の33章にある一節だ。
結局のところ、人間はどれだけ多くの物を手に入れても欲望に支配されている限り、心は常に不足や欠乏を感じ続ける。だからこそ、幸福であるためには足りないものではなく、与えられているものに意識を向けなくてはならない。
これは決して成長や向上を否定するものではないし、進歩・発展しなくてもいいという意味でもない。成長・向上・進歩・発展を目指すことと、いま与えられている恩恵を認識することはトレードオフの関係ではないからだ。
「足るを知る心」を育むためには日常の中にある「小さな幸せ」を意識的に見つけることが重要となる。
大切なのは「それがなければ不幸」と考えるのではなく、「それがあったら最高だが無くても自分は幸せだ」という意識の向きだ。
それこそが心豊かで幸福な人生を歩む上で大切なことだと僕は思っている。
欲しけりゃ求めるな。



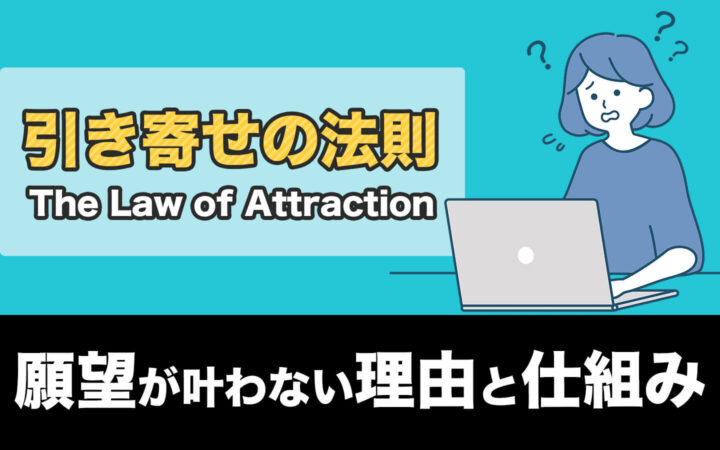

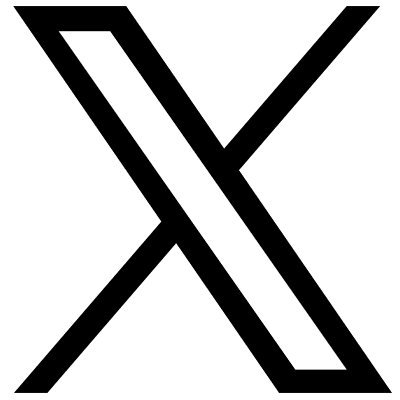
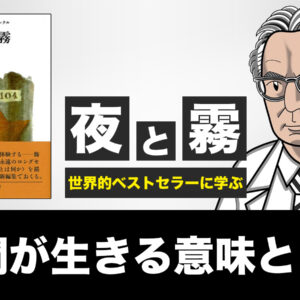
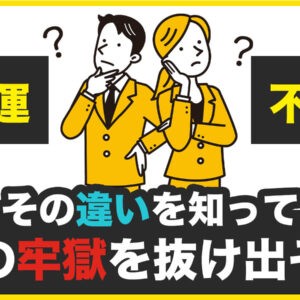
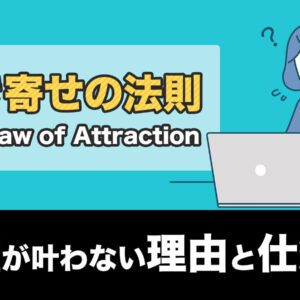


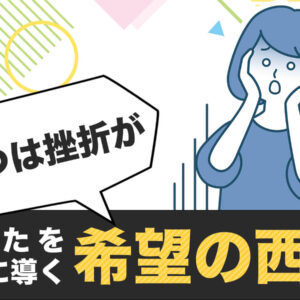




この記事へのコメントはありません。