我々が認識している現象は心がつくり出したもの
僕たちが認識していることは本当に絶対的な真実なのだろうか?
あなたの目に映るもの。
あなたが正しいと信じて疑わない考え。
あなたを取り巻く環境。
それらは本当に絶対的な真実といえるのか?
それらは客観的に存在しているように見えるが、じつは心の働きがつくり出した幻想にすぎないかもしれない。
仏教には「唯識(ゆいしき)」と呼ばれる思想がある。
唯識とは、我々が知覚している世界は心の認識作用によって現れているものであり、独立して存在する客観的な実体はないとする考え方だ。
この唯識思想をわかりやすく表現したものが「一水四見(いっすいしけん)」である。
一水四見|同じものを見ても人によって解釈は異なる
一水四見とは、ひとつの水でも見る立場によって異なる姿に映るという教えだ。
- 人間は「水」と見る
- 魚は「住処」と見る
- 天人は「瑠璃の水面」と見る
- 餓鬼は「血膿の池」と見る
これは「人間」「魚」「天人」「餓鬼」の立場で「水」を見た場合、それぞれ異なるものに見えることの例えだ。
認識の主体が変われば認識の対象も変化する。
つまり同じものを見ても人によって解釈は異なるのだ。
我々はみんな己の心のフィルターを通して世界を見ている。
そこに気が付かなくてはならない。
物事の本質をあるがままに捉えているのではなく、心がつくり出した表象を真実だと思い込んでいるにすぎないのだ。
そして、この一水四見という考え方に人間関係の大きなヒントがある。
人間関係の摩擦は「正しさと正しさの衝突」によって生じる
人間関係がうまくいかない人には一定の共通点がある。
そのひとつが自分の思想や認識を絶対視し、他者の価値観や考え方を受け入れられないことだ。
- 「その考えは間違っている」
- 「正しいのはこうだ」
- 「人間としてこうあるべきだ」
こうした姿勢は「自分が正しく、相手が間違っている」という頑迷固陋な態度に他ならない。
どうだろうか?
人間であれば誰しも少なからず心当たりがあるだろう。
僕も例外ではない。
しかし本当に自分が正しく、相手が間違っているのだろうか?
その逆の可能性はないだろうか?
もしかしたら両方とも一理あるかもしれないし、両方とも見当違いかもしれない。
そもそも善悪や正誤の物差しは誰が定めたものなのか?
僕を含め、「自分が正しく、相手が間違っている」という考えに囚われたときは一呼吸置き、「一水四見」の視点を思い出すことが大切だ。
あなたが正しいと信じている考え方は、あなたの心のフィルターを通して見た世界にすぎない。相手もまた別のフィルターを通して己が正しいと信じる世界を見ている。
争いは正義と正義のぶつかり合いによって生じているのだ。
「相手が間違っている」のではなく「自分とは異なる」だけ
唯識の基本的な考え方を思い出してほしい。
「我々が知覚している世界は心の認識作用によって現れているものであり、独立して存在する客観的な実体はない」
これは正誤や善悪は人間の尺度で作られた相対的な認識にすぎないということだ。大きな視座から見れば、究極的には正も誤も善も悪も存在しない。
相手が「間違っている」のではない。
ただ「自分とは異なる」だけなのだ。
我々はそれぞれ異なるフィルターを通して世界を認識している。
一水四見。
この視点を持つだけで人間関係の摩擦や衝突が驚くほど減るだろう。
意見の対立や見解の相違があっても、相手が間違っていると一方的に断罪するのではなく、「異なる世界の見え方」「自分にはない価値観」として受け入れやすくなるはずだ。
「異なる意見や価値観をすべて受け入れろ」という意味ではない
ひとつ注意すべきポイントがある。
- 「相手が間違っているのではなく自分とは異なるだけ」
- 「大きな視座から見れば究極的には善悪も正誤もない」
こうした考えを拡大解釈すると、「暴力や迫害も相手の立場から見れば正しいのか」といった極論が浮かぶかもしれない。
当然ながらそうではない。
それは唯識思想の要点を逃している。
唯識思想が示しているのは「同じものを見ても立場や心の状態によって解釈は異なる」という事実であって、「どんな行為もすべて許される」という無秩序を肯定しているわけではない。
人間社会には共同体を維持するための規範や倫理が存在する。それを守らなければ他者はもちろん自分さえ傷つける結果となり、社会そのものが成り立たなくなってしまう。
本来、その規範や倫理さえも広い意味では人間がつくり上げた「フィルター」ではあるが、少なくとも我々がこの社会の中で安心して暮らすためには、それらの共通ルールに依拠せざるを得ない。
唯識思想が教えてくれるのは、そうしたルールを無視してよいということではなく、「己の考え方や解釈が絶対的なものではない」という洞察なのだ。
「正しさ」という思い込みを手放すと人間関係が楽になる
一水四見の考え方をベースに「自分が正しい」「相手が間違っている」という二元論を放棄しよう。
すると途端に人間関係が楽になる。
人間関係が楽になるというのは、誰とでも仲良くなれることではない。人間関係に対する執着から開放されるということだ。
僕たちはつい「自分の意見に賛同してくれる人は味方」で、「意見の合わない人は自分を否定する敵」と考えてしまいがちだ。
しかし価値観が異なるからといって無理に拒絶する必要はない。合わないなら合わないで「そういう考え方や見方もあるのだな」と受け止めればいい。
その一方で意見が合うからといって無条件に受け入れるのもまた危うい。価値観が似ているからといって、その人の考えが理にかなっているとは限らないからだ。
大切なのは「自分と相手は異なるフィルターを通して世界を見ている」という事実を忘れないこと。
人間は水を「水」と見て、魚は水を「住処」と見る。
天人は水を「瑠璃の水面」と見て、餓鬼は水を「血膿の池」と見る。
そのどれもが正解でありながら、同時にどれもが正しくない。
水はただの「それ」なのだ。


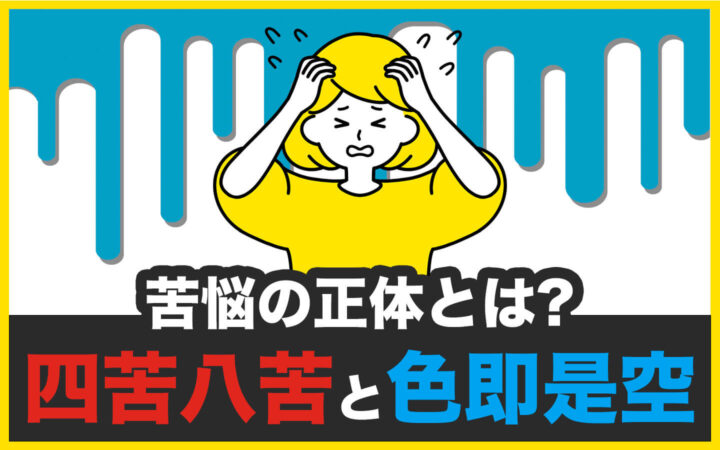
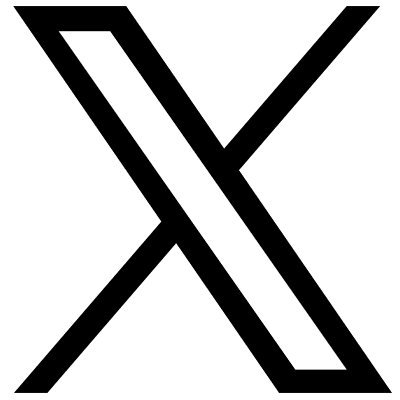
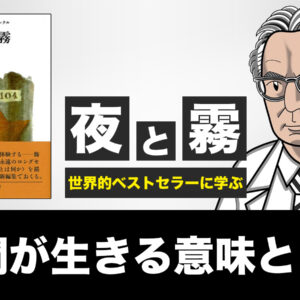
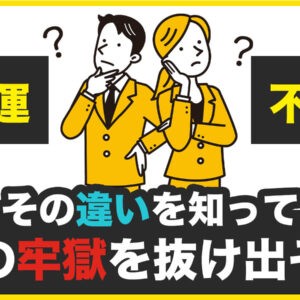
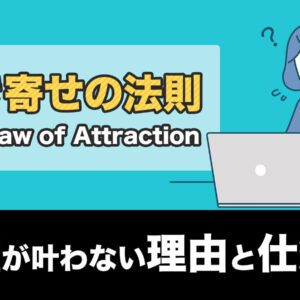


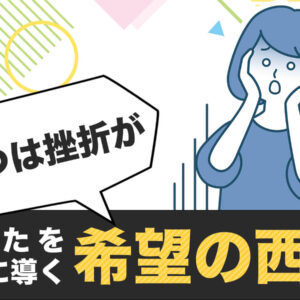




この記事へのコメントはありません。