引き寄せの法則は「心のありようが現実になる法則」
何年も引き寄せの法則を実践しているが、いつまでたっても願望が叶わない。
とくに自分にとって最も重要な願望 ──
いわゆる本願が叶わない。
そんな人は根本的な部分を取り違えている可能性がある。
引き寄せの法則は「願望が現実になる法則」ではない。
「心のありようが現実になる法則」だ。
引き寄せの法則は霊性的なスピリチュアルの法則という見方もできるが、僕は極めて現実的で心理学的な仕組みと解釈している。
まず引き寄せの法則についておさらいしてみよう。
引き寄せの法則とは?
思考が現実を創造する法則。
自分の感情や波動と共鳴する出来事が自然と引き寄せられるという考え方。
今回はいわゆる「引き寄せ難民」と呼ばれる人に向けて、なぜ引き寄せの法則を実践しても願望が叶わないのかを心理学的な観点から解説していく。ぜひ最後まで読み進めてほしい。
引き寄せの法則の心理学的なメカニズム
先に結論から言おう。
引き寄せの法則で願望が叶わない人は「願望が現実になっていない」のではない。
「叶わない自分が現実になっている」のだ。
つまり「叶わない」が「叶っている」といえる。
これは言葉遊びではなくそのままの意味だ。
「叶わない」が「叶っている」。
この意味を理解するためには、心のありようが現実を形づくる仕組みを知らなくてはならない。
心のありようが現実になる仕組み「カラーバス効果」と「予言の自己成就」
人間の脳は重要だと感じた情報を優先的に処理する「選択的注意」という機能が備わっている。たとえば「赤い色」に意識を向けると、途端に周囲の赤いものが目に飛び込んでくる。
この意識を向けた対象に関する情報が目に入りやすくなる心理現象を「カラーバス効果」という。
人は常日頃から意識を向けている考え方や価値観を通じて信念を形成する。そして心の奥底にある信念に基づいて言動や行動を選択し、無意識のうちに深層心理にある思い込みを現実にしようとする心理作用が働く。
このように無意識の信念が行動を通じて現実となっていく現象を「予言の自己成就」と呼ぶ。
つまり日常的に意識している思考や価値観がカラーバス効果で強化され、それが深層心理の信念として定着する。その信念が行動の引き金となり、最終的にその信念に相応しい出来事が予言の自己成就によって現実化するのだ。
これが引き寄せの法則の心理学的な仕組みであり、思考が現実を形づくる基本的な流れとなる。
- カラーバス効果
自分が意識している対象に自然と注意を向ける心理現象。 - 予言の自己成就
思い込みや期待が行動を生み、無意識にある信念が現実になる現象。
現実になるのは「願いそのもの」ではなく「願いの動機」
冒頭で述べたように、引き寄せの法則は「願望が現実になる法則」ではなく「心のありようが現実になる法則」だ。
そして現実を創造するのは「願いそのもの」ではなく「願いの動機」だ。それは「願望の動機」が「現実という結果になる」ことを意味する。
つまり動機と結果はイコールであり、動機が結果に帰結するのだ。
ここで「お金に恵まれない人」と「お金に困らない人」を例として、願いの動機が現実という結果を創造するプロセスについて考えてみよう。
お金に恵まれない人
お金に恵まれる人とお金に困らない人では、基本的に「お金に対するスタンス」が異なる。
お金に恵まれない人は「お金が足りないからもっと欲しい」「惨めな思いをしたくないからお金を稼ぎたい」といった欠乏動機を起点としている場合が多い。
つまり願望の動機は「欠乏の補完」だ。
このタイプは、どうにかして今すぐお金を得ようと焦り、目先の儲け話に飛びついたり、ギャンブルや宝くじのような期待値の低い手段に頼ったりしがちだ。当然、お金に恵まれるはずもなく、その満たされない心を埋めるために浪費に走ったりもする。
こうして「お金に困っている自分」というセルフイメージが潜在意識に浸透し、その信念のままにお金に恵まれない現実が創造されるのだ。
お金に困らない人
お金に困らない人は「お金そのもの」を追求しているのではなく、「お金をどう活用するか」という成長動機を起点にしている場合が多い。「お金をどう使えば人生がより良くなるか」を常に考えており、金融や投資の知識を学ぶために自己投資を惜しまない。
このタイプの願望の動機は「充足の拡大」だ。
たとえ現状の収入が少なく、生活にゆとりがなかったとしても可能な限り質素倹約に努め、収入が少ないなりに貯蓄を続けるだろう。一攫千金を狙ったギャンブルや見栄を張るための浪費など論外だ。
意識の焦点が「お金を通して得られる経験や価値」に当たっており、資産形成や事業の発展といった形で着実な成果に結びついていくはずだ。そして「自分は豊かである」というセルフイメージが定着し、その心のままに経済的に豊かな現実が創造されるだろう。
お金に恵まれない人もお金に困らない人も、どちらも「お金を求める動機」がそのまま現実という結果に帰結しているのだ。
- お金に恵まれない人は「欠乏を補うため」にお金を求める。
その動機が「常に足りない」という結果に帰結する。 - お金に困らない人は「充足を拡大するため」にお金を求める
その動機が「すでにある」という結果に帰結する。
「引き寄せ難民」といわれる人の願望が叶わない理由
いわゆる「引き寄せ難民」といわれる人たちは、願望の起点が「欠乏感」に基づいている場合が多い。
一体なぜ必死にアファメーションやイメージングをするのだろう?
どうしてそれほどまでに願望を叶えたいのか?
それは足りないからだ。
無いからこそ願い望む。
だから「願望」なのだ。
あなたの心には大きな穴が開いている。たとえば「金銭の欠乏」「恋人の欠乏」「愛の欠乏」「承認の欠乏」「名誉の欠乏」「社会的地位の欠乏」。こうした欠乏感を埋めてくれるものを願い望む。
足りていないから欲しい
欠けているから埋めたい。
叶っていないから叶えたい。
こうしてあなたの心のままに現実が創造されていく。
もちろん創造されるのは「願望が叶った自分」ではない。
その欠乏感を映し出した「叶っていない自分」だ。
そしてアファメーションやイメージングなどに取り組むほど願望の実現は遠のくだろう。そうした取り組みが「叶っていない自分」をさらに強化してしまうからだ。
アファメーションやイメージングが無意味ということではない。そうではなくて「叶っていない自分」が願望を叶えようとしても、現実になるのは「叶っていないから叶えようとする自分」なのだ。
人生は思い通りにならないと人々は言う。
しかし真理は逆説の向こうにある。
人生は自分が心の奥底で信じている通りにしかならないのだ。
願望が叶わなくて苦しいのなら願いを手放す勇気が必要
願望を追いかけても叶う気配すらなく、むしろ苦しみが増していく。
もしもそんな状態にあるのなら、願いそのものを手放す勇気が必要かもしれない。願望に執着すればするほど「叶っていない現実」が固定され、欠乏感や不足感という信念を強化してしまうからだ。
願いを手放すとは諦めることではないし、「叶わないからもうどうでもいいや」と投げやりになることでもない。そうではなくて「願いが叶っても叶わなくても、自分はすでに満たされている」という感覚を取り戻すことだ。
探し物は探していないときに見つかる
「願望が叶えば幸福」で「願望が叶わなければ不幸」という二元論に囚われている人は少なくない。
いわゆる引き寄せ難民と呼ばれる人たちは、心の基準値を「願望が叶えば+100ポイント」で「願望が叶わなければ-100ポイント」と設定する傾向にある。
しかし本来は願望が叶わなくても「±0ポイント」で何も失われはしない。むしろ失敗や間違いという経験から学びを得られるわけだから、ポイントが加算されると考えることもできるだろう。
そもそも人間は生きているだけで100点満点であり、人生に減点など存在しないのだ。
願望が叶えば最高だが、たとえ叶わなくともそれはそれで最高。
どっちに転ぼうとも私は幸せだ。
そう思えるようになったとき、あなたの心は充足で満たされる。そのとき欠乏感や不足感を出発点とした願望は自然と消え去るだろう。
すでに満たされているあなたは何も必要としない。
そしてここが引き寄せの法則の不思議なところなのだが、何も必要としなくなったあなたには、あなたが求める以上のものが与えられる。
失くした探し物は「もういいや」と探さなくなったときにこそ見つかるのだ。

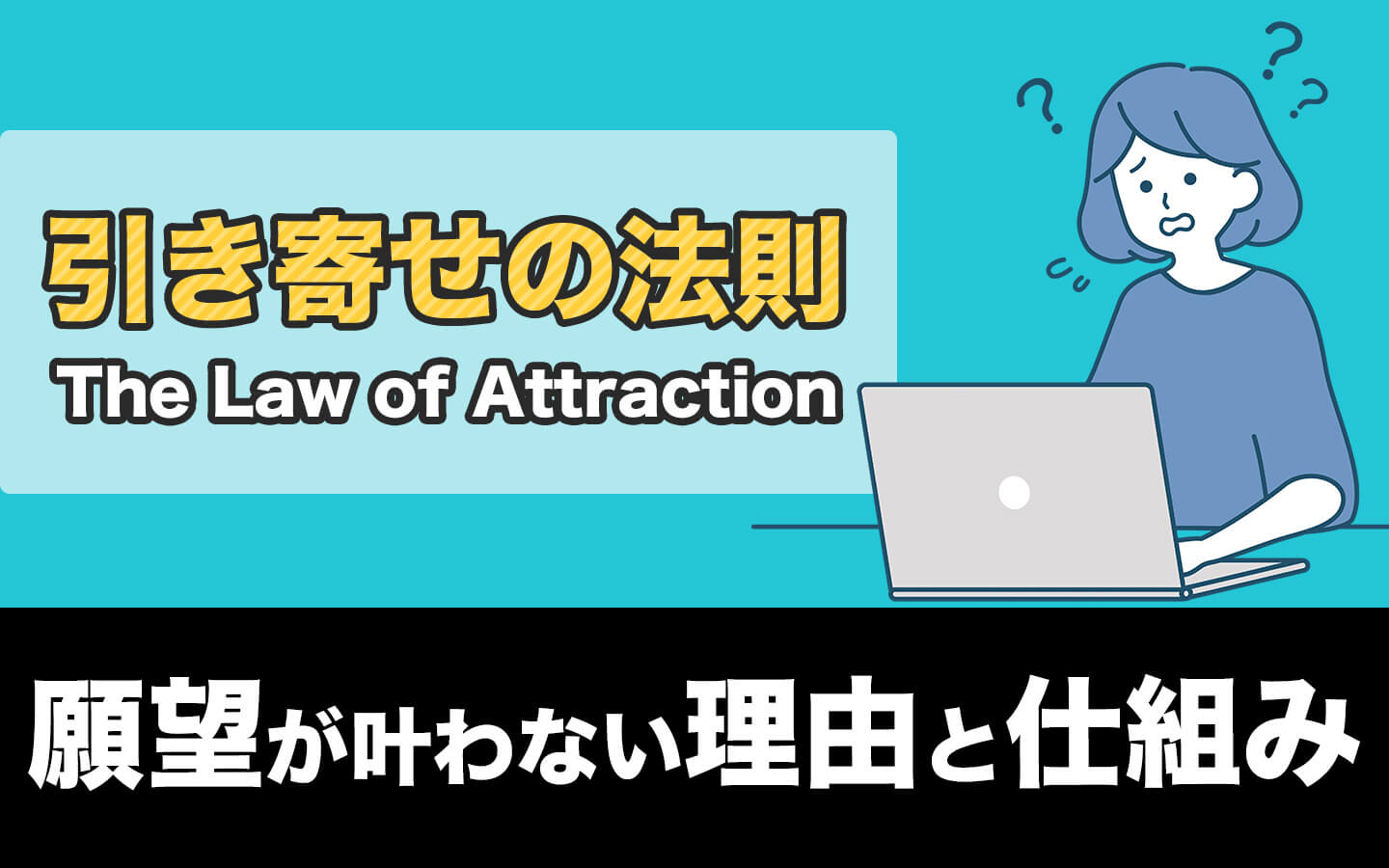



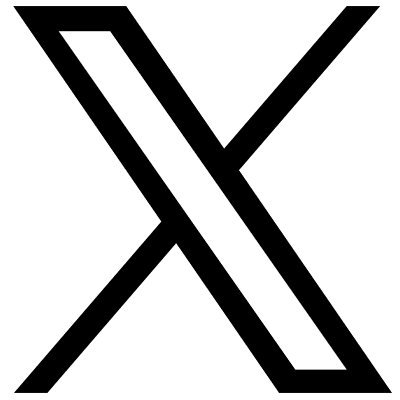
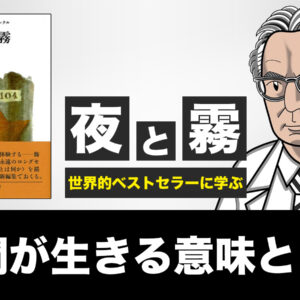
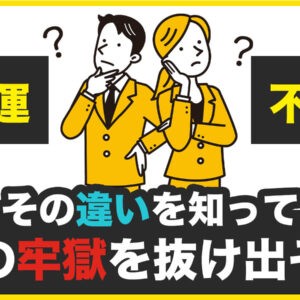
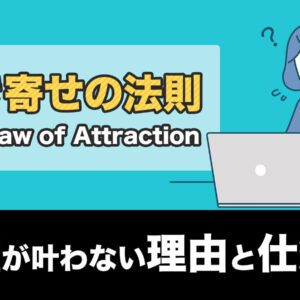


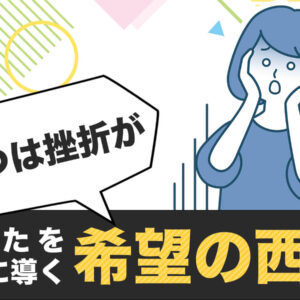




この記事へのコメントはありません。