自信のなさは欠点ではなく才能の裏返し
自分に自信がない。
もっと自分に自信をもちたい。
堂々と胸を張って生きたい。
そんな悩みを抱えている人は決して少なくない。
先に結論から言おう。
あなたは変わる必要なんてないし、無理に自信をもとうとする必要もない。唯一必要なことは「自分は自分のままでいい」と思えない自分を許すことだ。
「自分に自信がない」というその性質は、じつはひとつの能力であり才能だ。これは上辺だけの綺麗事や取り繕った精神論ではなく、心理学や生物学の観点から説明できる。
今回は「自分に自信がない」と悩む人の性格的な特徴を考察するとともに、その性質がもつ長所について解説していくので、ぜひ最後まで読み進めてほしい。
自分に自信がないと悩む人の性格的な特徴
自分に自信がないと悩む人には、いくつか共通する性格的な特徴がある。代表的な要素として挙げられるのが以下の5つだ。
- 自分に対する評価が厳しい
- 自分と他人を比較する
- 失敗や間違いを過度に恐れる
- 他者からの評価を気にする
- 他者を優先して自分を後回しにする
多くの人はこれらの特徴に対してマイナスの印象を受けるかもしれない。
しかし、ここで重要なのはプラスとマイナスは表裏一体の関係であり、メリットは裏返すとデメリットに通じるということだ。
たとえば「明るい人」は「うるさい人」にもなり得るし、「物静かな人」は「冷たい人」とも捉えられる。「社交的な人」を「馴れ馴れしい人」と感じる人がいれば、「優しい人」を「頼りない人」と認識する人もいるだろう。
このようにプラス・マイナスやメリット・デメリットは固定的なものではなく、視点によって変化するものだ。
自信がないと悩む人の性格的な特徴も同じで、見る角度を変えると以下のように解釈できるだろう。
- 自分に対する評価が厳しい
自分の能力や成果を客観的に見抜く力がある。 - 自分と他人を比較する
他者の長所や短所を分析する観察力に優れる。 - 失敗や間違いを過度に恐れる
行動に伴うリスクを予測する能力に長けている。 - 他者からの評価を気にする
周囲の期待やニーズを敏感に察知する力がある。 - 他者を優先して自分を後回しにする
周囲の調和を大切にできる協調性や思いやりに富む。
これらを総合すると「自分に自信がない人」は己の能力を過大評価せず、自分と他者を客観的に観察・評価し、リスクを予測しながら周囲の期待や調和にも配慮できる人物といえるだろう。
これらはビジネスの分野でいえば計画の立案・策定や競合調査、リスク管理、プロジェクトマネジメント、チームビルディングなどで欠かせないスキルとなる。
繰り返すがプラスとマイナスは表裏一体の関係であり、メリットを裏返すとデメリットに通じる。
「自分に自信がない」と悩んでいる人の多くは、自分の能力や才能のマイナスの側面だけを見て評価しているにすぎないのだ。
能力が低い人は自分を過大評価し、能力が高い人は自分を過小評価する
人間は能力の低い人ほど自分の実力を正確に評価できず、実際よりも過大に評価する傾向にある。一方、能力の高い人ほど自分の課題や問題を客観的に認識できるため、自分を過小に評価してしまう。
これを心理学では「ダニング=クルーガー効果」と呼ぶ。
つまり能力の低い人ほど自信に満ち溢れ、能力の高い人ほど謙遜すると言い換えることもできる。
たとえばボクシングの世界ランカーが己の武力を誇示するだろうか?高圧的な態度で他者を威嚇するのは街のチンピラで、本当の強者は礼節を備えているものだ。上場企業の創業者やプロのトップアスリートが大金をひけらかすだろうか?それをするのは小金持ちか詐欺師だろう。
もちろんこれは極端な例だが、あながち的外れでもないはずだ。
それと同じで「自分に自信がない」という人は物事の課題や危険を察知する能力が高すぎるがゆえに、一般的な人には認識できない自分の弱点や物事の不安要素が見えてしまうのだろう。
そういう意味では自信満々で楽観的な人はポジティブなのではなく、物事の裏に潜む課題や問題を単に認識できていないだけという可能性もある。
「自分に自信がない」という感覚は謙虚さや有能さの裏返しであり、それは根拠なき楽観よりも遥かに貴重な能力なのだ。
狩猟採集時代の人間は生き残るために「ネガティブな性質」が不可欠だった
人類の歴史は原人まで遡ると約700万年といわれており、農耕が始まる約1万年前まで狩猟採集時代だったと考えられている。
そして狩猟採集時代の人間にとって「ネガティブな性質」は生存に欠かせない重要な能力だったはずだ。
狩猟採集時代の環境では常に肉食獣や他部族などの脅威に晒されており、食料の欠乏や自然災害のリスクも大きかっただろう。水道やガスなどのインフラが整備されているはずもなく、現代のような医療技術もないので、小さなケガや病気でも死に直結する可能性がある。
このような不確実で危険な環境を生き抜くためには、「きっと大丈夫」「何とかなるだろう」という根拠なき楽観よりも、「危険かもしれない」「念のため避けよう」という臆病さや警戒心が必要だ。
もちろん、獲物を狩るためには未知の領域に踏み出し、リスクを恐れないポジティブな性質も必要となる。
いわゆる「ポジティブなタイプ」は探索や狩猟に適しており、「ネガティブなタイプ」は集落の警戒や安全管理を担う役割を果たす。つまり人間の生存戦略としてはポジティブタイプとネガティブタイプの両方が必要で、それぞれが役割分担的に集団の生存を支えていたと考えられる。
現代ではポジティブな性質は「良」で、ネガティブな性質は「悪」と思われがちだが、それは物事の表面しか見えていない人々の誤った認識だ。ネガティブな性質は欠点ではなく、危険の回避や種の存続に直結する重要な才能なのだ。
「自分に自信がない」と悩む人は、ここでいうネガティブタイプの性質を色濃く受け継いだ人といえるだろう。それは決して「劣っている」ということではなく、むしろ進化の過程で人類が生き残るために欠かせなかった「優れた資質」の名残といえる。
ポジティブタイプの役割
- 未知の領域に踏み出す探索や狩猟に向く
- リスクを恐れず挑戦し、新しい資源を獲得する
- 集団に活力や希望を与える
ネガティブタイプの役割
- 危険を予測し、最悪の事態に備える
- 環境の変化や不審な兆候に敏感に反応する
- 集団内で警戒や安全を担う役割を果たす
それでも自分に自信がもてないというあなたへ
「自分に自信がない」というその性質はひとつの能力であり才能だ。しかし理屈として理解できても、心で納得するのは難しいかもしれない。
人間の性格や性質は先天的要素だけで決まるものではなく、育った環境や人間関係といった後天的要素の影響を大きく受ける。とくに両親に否定されて育った人、あるいは理解ある友人が周りにいなかった人は自分を否定しがちな傾向にある。
そうした人が心理学や生物学の観点から見れば「自信のなさ」は一種の才能だと言われて、「では今日から自信満々に生きます」となれば誰も苦労しない。
それでいいんだ。
自分に自信なんてなくていい。
自信の源泉は外的な評価ではなく「自己受容」にある
他者と比べて優れているから価値があるのではなく、他者と比べて劣っているから価値がないということでもない。あなたという存在そのものにすでに意味があるのだ。
自己受容とは、そうした「ありのままの自分」を抱きしめる態度だ。だからこそ、あなたは変わる必要なんてないし、無理に自信をもとうとする必要もない。
それでも「ありのままの自分でいい」と思えない人も多いだろう。
それでもいい。
冒頭で述べたように、そんなあなたに唯一必要なことは「自分は自分のままでいい」と思えない自分を許すことだ。あなたが他者にやさしくするように、自分自身にほんの少しだけやさしさを分けてあげてみよう。
「私は私のままで人生を楽しんでいい」
そう唱えてみてほしい。
あなたが本当に欲しているのは形だけの自信などではなく、今その心に開いたもののはずだ。
大切なのは「自分は自分のままでいい」と思えない自分を許すこと。



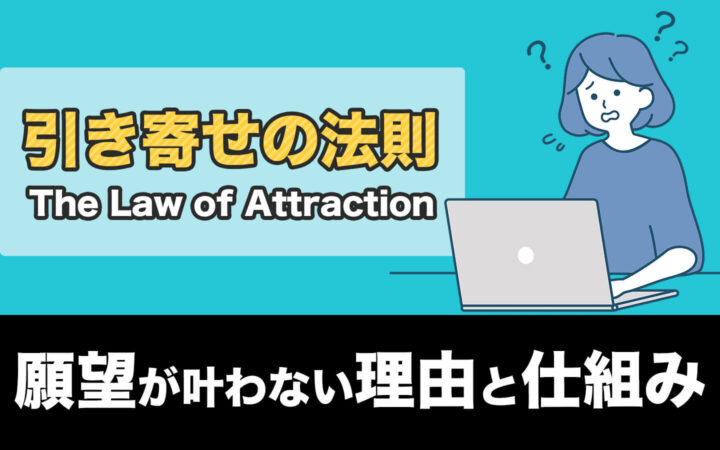

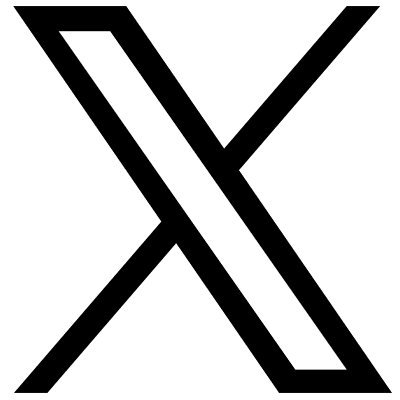
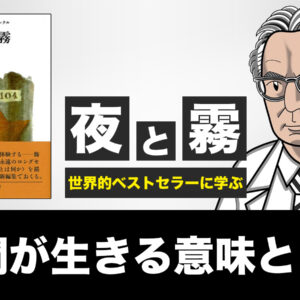
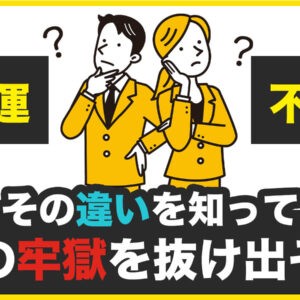
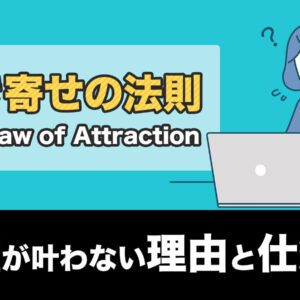


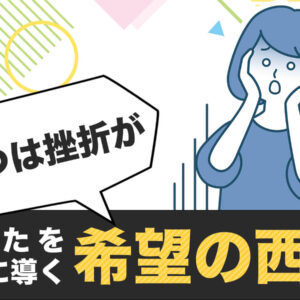




この記事へのコメントはありません。