行動できないのは臆病や怠惰ではなく自然な心理作用
あなたはこんなふうに思ったことはないだろうか。
- 新しいことに挑戦したいのに行動できない
- 何かを始めても三日坊主で終わってしまう
- がんばりたくてもがんばれない
- 「やるぞ!」と決意しても気づけば元の生活に戻っている
- やらなきゃいけないとわかっているのに先送りしてしまう
先に結論から話そう。
これらは「現状維持バイアス」と「自我消耗」と呼ばれる心理作用による自然な現象だ。
新しい挑戦や努力の継続が難しいのは、決してあなたが臆病だからでも怠惰だからでもない。
僕たち人間の脳は変化を嫌い、現状維持を好む。そして現状を変えようと努力すればするほど精神力が枯渇する。それは怠惰なのではなく、弱肉強食の世界を生き残るためにDNAに刻み込まれた脳と心の防御機能なのだ。
今回はがんばりたくてもがんばれない理由について心理学の視点から解説していく。
とくに自分を変えたいのに変えられないと悩んでいる人は、ぜひ最後まで読み進めてほしい。
現状維持バイアス(Status Quo Bias)
現状維持バイアスとは、変化よりも現状維持を好む心理的な傾向のことだ。
人間の脳は新しい環境や馴染みのない行動を「未知で不確実なもの」と捉える。そして不確実性にはリスクが伴うため、進化の過程において「生命の安全を確保するために現状を維持する」というプログラムが組み込まれてきたと考えられる。
たとえば野生の動物は基本的に縄張りから出ない。見知らぬ道の先には捕食者や未知の危険、食料不足といったリスクが潜んでいるかもしれないからだ。
- 熊は毎年同じ川や木の実の場所を訪れる
新しい食料源を探すよりも確実に食べられる場所を優先する。 - 鳥は巣が多少壊れていてもすぐには場所を移らない。
巣の移動は捕食者との遭遇や悪天候の危険があるので巣を修理しながら使い続ける。 - アリは巣作りや餌運びのルートをほとんど変えない
新たなルートを試行錯誤よりも過去に安全だった道を踏襲する。
人間も同じで、たとえ「新しいことを始めたい」「自分を変えたい」と強く思っても、無意識のうちに行動や習慣を変えることに慎重になる。現状との変化が大きれば大きいほど脳は「変化=危険」と判断し、がんばりたくてもがんばれない状況に陥ってしまうのだ。
そして意を決して新しいことを始めたとしても、無意識の内に元の自分に戻ろうとする。禁酒や禁煙、ダイエットなどが三日坊主で終わりがちな理由はこうした心理作用によるものだ。
- 生物は基本設計として変化を嫌い、現状維持を好む
- 変化が大きいほど脳は「変化=危険」と認識する
- 変化を望んでも無意識のうちに元の自分に戻ろうとする
自我消耗(Ego depletion)
自我消耗とは、意志力のエネルギーが有限であり、使えば使うほど減少する心理作用のことだ。
僕たちは日常生活における数多くの場面で意志力を使っている。たとえば、以下のような「自分をコントロールする行為」はすべて意志力を消費する。
- やる気が出ないけれど仕事を続ける
- 上司の理不尽な発言をこらえる
- 面倒な書類整理を片付ける
- 食べたいラーメンやケーキを我慢する
- お酒やタバコを控える
- 行きたい遊びの誘いを断って勉強する
意志力はバッテリーのように有限だ。充電することなく使い続けるとやがてエネルギー切れを起こす。その結果、「やるべきこと」や「新しい挑戦」に取り組むエネルギーが残らなくなってしまうのだ。
米国の心理学者ロイ・バウマイスターは、意志力の消耗を示す有名な実験を行った。
参加者の学生を「クッキーを与えられるグループ」と「クッキーを我慢させられるグループ」に分ける。
与えられるグループ:おいしそうなクッキーを好きに食べられる。
我慢させられるグループ:クッキーが目の前にあるが食べられない。
その後、両グループに高難度のパズル(実際には完成できない)を解かせる。
<結果>
クッキーを与えられたグループ:平均19分粘った。
クッキーを我慢させられたグループ:平均8分で諦めた。
近年ではこの実験の再現性を疑問視する研究もあるが、「我慢が続くと行動力が落ちる」という事実に関して一定以上の相関はあるだろう。
- 人間の意志力はバッテリーのように有限
- 我慢や抑制に意志力を使うほど減少していく
- 意志力が消耗すると新しい行動に踏み出す力が残らない
現状維持バイアスを乗り越えようとするほど自我消耗が強く働く
なぜがんばりたくてもがんばれないのか?
なぜやらなくてはならないと分かっていてもできないのか?
その心理学的な仕組みをダイエットに例えて解説しよう。
あなたは夏までに5kg痩せることを目指して食事制限を開始する。
食事の量を減らしたり、甘いものや晩酌をやめたりすると摂取カロリーが急に減少するため、脳と身体は飢餓状態と判断し、基礎代謝を下げてエネルギー消費を抑えようとする。
この身体の状態(体温・体重・血糖値・免疫など)を一定に保とうとする機能を「恒常性(homeostasis)」と呼ぶ。
さらに、この変化への抵抗は心理面にも及ぶ。
脳は「今まで通りの生活=安全」と捉えているため、食事制限や禁酒といった新しい行動は現状維持バイアスによって拒否されやすくなる。そして「ちょっとくらい甘いものを食べてもいいよね」「もう一週間もお酒を我慢したから今日は特別」といった言い訳を無意識に生み出し、元の食習慣に引き戻そうとする。
この心理的な抵抗を乗り越えるためには強い意志力が必要だ。
ところが現状維持バイアスを突破しようとすればするほど意志力を消耗し、ダイエットに向かう気力やモチベーションを保てなくなる。
つまり、身体は恒常性によって変化を防ぎ、脳は現状維持バイアスで元の習慣に戻ろうとし、その抵抗を突破しようとするほど意志力を消耗して挫折するというわけだ。
これが新しいことへの挑戦や努力の継続が難しい心理学的な仕組みとなる。
現状維持バイアスと自我消耗の壁を乗り越えるためのアプローチ
現状維持バイアスと自我消耗は誰もが持つ「標準装備」の心理作用だ。冒頭で述べたように、生存戦略としてDNAに刻み込まれた脳と心の防御機能なのだ。
そして現状維持バイアスと自我消耗は変化の幅が大きいほど強力に作用する。生活習慣や行動を一気に変えようとしたり、今の自分から大きくかけ離れた目標を立てたりすると、その反発力も比例して大きくなり挫折しやすくなる。
そこで鍵となるのが、小さく始めて脳と身体への負荷を分散する「スモールステップの原理」だ。
スモールステップの原理(Small Steps Principle)
スモールステップの原理とは、最終的な目標や大きな課題を細分化し、段階的に取り組む方法である。
変化の幅を小さくすると脳はそれを「危険な変化」ではなく「許容できる調整」として認識しやすくなる。
たとえばダイエットの場合、運動習慣のない人が「毎日5km走る」という目標を掲げたり、「1日の摂取カロリーを1000kcalに制限する」といった極端な食事制限に取り組んでも、現状維持バイアスと自我消耗による反発で挫折する可能性が非常に高い。
そこで以下のように小さな習慣から始めると抵抗が最小限になり継続しやすくなる。
- 1日10分だけウォーキングをする
- 就寝前に3分ストレッチをする
- ご飯を大盛りから並盛に変更する
- 夕食後の飲み物は水かお茶にする
- おやつをスナック菓子からナッツ類に置き換える
なんだそんなことかと思うだろう。
だが、こうした小さな行動こそが大きな変化の土台になる。そして少しずつ食事制限や運動の強度を高めていくことでやがて当たり前の習慣となり、努力している感覚すらなくなっていくだろう。
1万円は1円が積み上がったものであり、川は一滴一滴の水で形づくられている。大樹が小さな苗から成長するように、健全な習慣も日々のごく小さな選択と行動の積み重ねで作られていくものだ。
自分も2013年頃からランニングを始め、今でも週5回程度のランニング&ウォーキングを日課としている。開始当初は20代の若者だったのに1kmすら走り切れず、ウォーキングから始めたのを覚えている。
あくまでも健康と体型維持が目的なので強度は軽めだが、「距離:3.5km・ペース:5分30秒/kmのランニング」と「距離:2.5km・ペース:10分30秒/kmのウォーキング」と、1日あたり6kmの有酸素運動を10年以上楽しみながら継続できている。
だからこそ最初の一歩は驚くほど小さく、簡単すぎるくらいでちょうどいいのだ。
スモールステップの原理はどんな場面でも活用できる
もちろんダイエットや運動習慣というのはあくまでも一例だ。スモールステップの原理は勉強や仕事など、人生におけるさまざまな場面で活用できる。
たとえば英語を勉強したい場合、いきなり毎日1時間の勉強を課すのではなく、「毎日1単語だけ覚える」「寝る前に英語の例文を1つ読む」といった小さな習慣から始める。
仕事も同じだ。膨大なプロジェクトを前にして手が止まってしまうなら、「まず5分だけ資料に目を通す」「最初の1行だけ書き始める」といった小さなタスクに分解すればいい。
こうして行動のハードルを極限まで下げることで、脳は「できない理由」を探す前に動き始める。そして一度動き出せば自然と次のステップにつながっていくはずだ。
遠回りに思えるかもしれないが、「急がば回れ」という言葉があるように、大きな成果を手にする最短ルートは着実な小さな一歩の積み重ねにあるのだ。
一番の近道は遠回りだった。
遠回りこそが俺の最短の道だった。
ジャイロ・ツェペリ『ジョジョの奇妙な冒険 Part7 スティール・ボール・ラン』
「がんばりたくてもがんばれない」と思っている時点で変わり始めている
真面目で優秀な人ほど行動できない自分を責める傾向にある。
しかし本当はがんばれないのではなく、脳と心があなたを「変化=危険」から守ろうとしているだけだ。
だから「自分は意志が弱い」「やっぱりダメな人間だ」などと思う必要はない。むしろ自分を責めるほど自我消耗で意志力が削られ、動き出すべきときに必要なエネルギーさえも失ってしまうだろう。
変化にはエネルギーが必要だ。そして、そのエネルギーを蓄える時間もまた必要となる。もしも今のあなたが「なかなか動き出せない」状態だとしても、それは怠けているのではなく新たな一歩に備えてエンジンを温めている期間だと思ってほしい。
何よりもダメな人間はそもそも自分をダメだとすら思わない。
「新しいことに挑戦したいのに行動できない」「がんばりたくてもがんばれない」と思っている時点で、あなたはすでにがんばっているし、変わり始めている証といえるだろう。
だから安心してほしい。
あなたはもう変化のスタートラインに立っているのだ。
本能を破るのはほんの少しの行動だ。



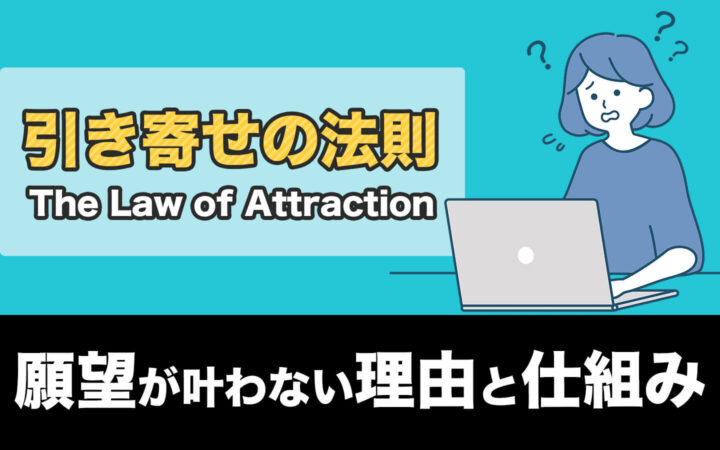

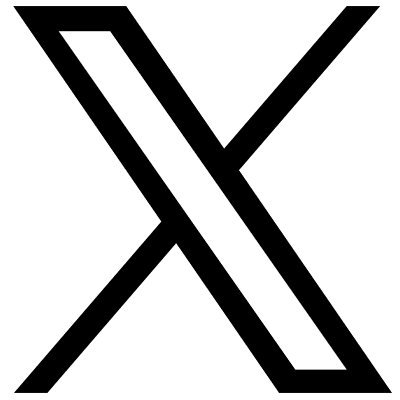
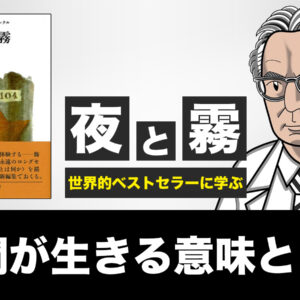
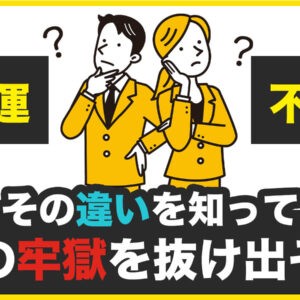
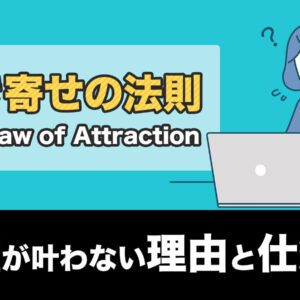


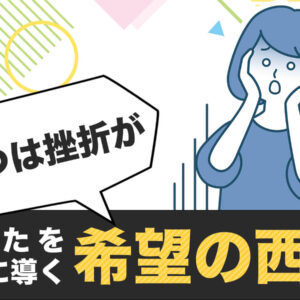




この記事へのコメントはありません。